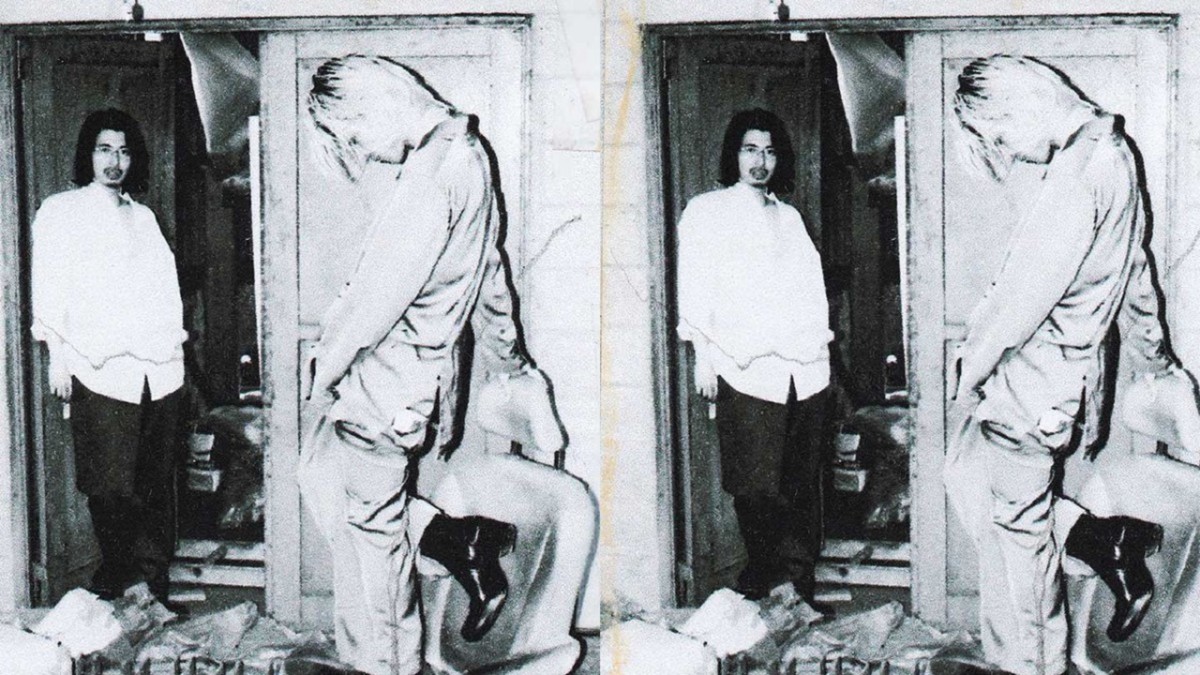
レビュー:Tohji, Loota & Brodinski『KUUGA』
2020年来、アンビエントな心象風景を作品に落とし込んできたTohjiとLootaが、フランスのプロデューサー・Brodinskiと辿り着いた共作EP。2021年3月31日リリース。
Track List:
1.Aegu
2.Yodaka Classic
3.Tob Recommend
4.Naked
5.Oni Classic
6.Iron D**k Recommend
7.Errday Recommend
8.Outro
異形の傑作
日本のHIPHOPにおいて後年、一種のシンギュラリティと位置付けられる作品かもしれない。
ゲリラ的にリリースされた『KUUGA』は、ラップとビート、リリックが渾然一体となって新境地を叩き出した大傑作だ。
直近の作品群で、これまで以上にHIPHOPの枠を飛び越える姿勢を明示してきたTohjiとLoota。
シングル単位でアンビエントやNu Disco的なアプローチをトライしてきた2人が辿り着いたのが、フランスのプロデューサー・Brodinskiとの邂逅、そしてグローバルな活動展開をあえて逆回転させたような、和風なテイストの導入だ。
全く和風な音使いがある訳でもない本作に漂うこの和の空気感を紐解く為、まずはリリックに着目したい。
リリックに込められた和の成分, 作詩表現の妙
全編を通してぼんやりと主軸に置かれたのは、虚ろな風景の中に浮かぶ遊女の姿だ。
そして彼女らに負荷的な刺激を与える存在の示唆。
彼女、あるいは彼女らは、逃れられない鉄格子の中で喘ぐ様をハナから暴かれて登場する(“AEGU”)。
そこから2人だけの行為に照準を当てた“Yodaka”では、愛情を伴ったメイクラブにも、本能的な肉欲とも読み取れる行為が暗喩的に描かれる。
ここで曲名になっている「夜鷹」も最下級の遊女の呼称として用いられていたものであり、遊女の、あるいはTohjiらの自己存在を位置付ける語句として作用する。
また、リリックの「はがれてくロール」も、かつての夜鷹が路上で性行為をする(*)際、ござや草むしろで人目を隠していたことを指すものと読み取れるなど、感覚的に奏でられる音の裏で、緻密な作詩作業のあったさまが窺える。
(*)高級な遊郭で雇われ、遊郭の部屋で行為に及ぶ花魁とは異なり、最下層の夜鷹は自分でごさやむしろを持ち歩き、路上で客引きし、その場で行為に及んでいた
以降もオーガズムの暗喩と取れる”Tob”, 遊郭の遊びとして発展したとされる「おにさんこちら」を用いた“Oni”, 作品中最も性行為の虚しさを直接的に描いた“Iron Dxxk”や“Errday”と続く。
中でも性行為のただなかを描いた“Iron Dxxk”が、逆に最も肉体的な表現から離れ、遊女の視点から無機質な、虚無的行為として描かれる詩的表現は特筆すべきものがある。
(Lootaのリリックも、とことんまで性行為の生物的側面を削ぎ落した表現を貫いている)
こうしてまずリリックだけを取り出すと、彼らが本作を「日本的な心象風景を融合した」と語る、その意味はかなりクリアになる。
根底にあるのは女性(たち)の目線であり、そこには日本的な遊女文化がそれとなく内在されているからだ。
そしてもちろん、そこにTohjiやLootaらしい現代的表現やボースティングも混在することで、本作は一義的な解釈を拒む、独自の生得領域を持つ。
このようなリリックの観点から『KUUGA』が優れているのは、これら要素を一聴しただけでは深層心理を刺激する程度にしか匂わせない、ある種奥ゆかしい表現に留めている点だ。
加えて日本語詩の美しさもさることながら、要所要所に挿入される「Iron Dxxk」, 「Naked」といったストレートな単語表現はピンポイントで英語に直すテクニックも効いている。
恐らく無意識的なものとは思うが、本作で描く残酷で本能的な世界を、1枚言語フィルターを通してから感じさせる。
あえてリスナーにダイレクトな歌詞理解をさせない、距離を取らせる表現手法として作用している要素だろう。
ビートとラップの共振
こうしてみるとその綿密な作詩作業が窺えるのだが、本作が傑出しているのは、これを例えば和風のビートに乗せると言ったストレートに「見せすぎる」行為を避け、あくまでBrodinskiと最先端のビートで融合することを目指した点だ。
Brodinskiは外部の楽曲でのプロデュース作品だと外形のくっきりとした音を届けることも多いが、自己名義の作品になると(特に近年では)より彼のオリジンに近い、良い意味で捉え所のないビートを届けることも多い。
そんな彼の可塑性の高い性質を最大限に利用して効果を発揮したのが『KUUGA』と言える。
ここで重要になってくるのが、当然だがビートとラップとの噛み合わせだ。
この点において今回のBrodinskiは、作家性の矜持は保ったまま、必要以上にビートでの主張を行わない。
主軸にあるのはラップとの接合・融合であり、この点において『KUUGA』はかなり緻密な連携が窺える。
特に“Yodaka”は、行為中の呼吸音を模したようなSEから始まり、その吐息の流れのままTohjiの第一声に繋がるイントロ部分、「俺らヨダカ」のリリックとシンクロしてTohjiの発声をチョップしてビートに置き換える部分、要所要所でのキックのインサートなど、こうした「ラップとの接合」を如何に丁寧に行ったか、その試みがよく分かる楽曲と言える。
呼吸音・発声が拍の役割を代替してそのままビート・ラップのスイッチングが行われるのは、他にも“Oni”などでも見られる本作の特色だ。
今回のビートではとにかく「抜き」が多用される。
これがラップに注意を向ける作用を持つ訳だが、ここで活きてくるのが(主にTohjiの)抜き部分で必ずパーカッシヴなラップの打ち方、ないしファルセットを用いてドラムレスな部分の盛り上げを行う意識だ。
“Naked”などはその典型例と言えるし、後半になるとビートのほぼ全てをTohjiの声で構成したような“Oni”も同様だ。
要は「ビートはその作家性を保ったまま、可能な限り抜く」 「代わりにラップはその間を埋める歌唱表現を求められる」という、双方に高難度な宿題が課された構成になっている作品が『KUUGA』だ。
そして、このハードルを乗り越えたことにより、特にTohjiのラップは「ビートを代替するパーカッションとしてのラップ」 「上ネタを代替するファルセットとしてのラップ」という、この歌唱法における、楽器的表現の幅を示すことに成功した。
ビートとラップが共にその屹立を乗り越えたからこそ、綿密に練られたリリックという素材を、音的な表現法として最大限高度かつアップデイテッドな形で示しすことに成功したのだと言える。
リリックの練り込みを下地に、ビートとラップが共に何を補い合えるか、何を高め合えるのか。
それを最先端の3人で、一切の妥協なく成し遂げたからこそ本作は傑作として結実した。
冒頭で本作がシンギュラリティになるかもしれないと書いた。
しかしこの域に達するまでに求められるワークロードを鑑みると、あるいは他の誰も到達出来ない極北となるかもしれない。
いずれにせよ、いまこのとき触れておくべき作品であることは間違いない。
これを3月末という2021年の早い段階でリリースしたのは、残りの8か月間、咀嚼する時間を与えてくれた彼らなりの優しさだろう。
───
2021/04/27 Text by 遼 the CP
インタビュー・コラム・レビュー執筆依頼・寄稿などについてはHP問い合わせ欄、あるいは info@prks9.com からお申し込み下さい。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。










この記事へのコメントはありません。