
対談(前編):つやちゃん x 遼 the CP(PRKS9) 『わたしはラップをやることに決めた』 – そこで誰が埋もれてきたのか?
1月28日、DU BOOKSより、つやちゃんによる書籍『わたしはラップをやることに決めた』が発売された。女性のHIPHOPアーティスト達が発表してきた作品、抱いてきた想いをすくい上げた本書は、日本のHIPHOPにおいて光が十分に当たってこなかった領域を確かに照らして見せた。
もちろん本書は(著者が書籍内で記す通り)始まりに過ぎない。本書を唯一無二の成果とせず、本格的に彼女たちの作品、そこで成し得た功績を語り続けるのは、「HIPHOPシーン」なるものがあるのであれば、その全体で求められる作業だろう。とは言うものの、もちろん本書がその熱量で掘り起こしたものも凄まじい。各アーティスト達への論考に始まり、後半には約200タイトルのディスクガイドを掲載。
この圧倒的なボリュームで紡がれた本書を手掛かりに、今回PRKS9ではつやちゃんとの対談を実施。前編では本書の掲げるメッセージから、このカルチャーのあり方を語り合った。後編では200タイトルのディスクガイドを元に作品談義、及びそこから見えてくるものについて語り合う。
つやちゃんによる公式プレイリスト:
サウスのラップが持つ身体性
遼 the CP:
この度は『わたしはラップをやることに決めた フィメールラッパー批評原論』の発売おめでとうございます。日本のHIPHOPにおける「女性」を切り取った素晴らしい本作に関連して、今日は色々お話させて下さい。まずはつやちゃんさんについて、簡単なご経歴を聞かせて頂ければと。元々どのようにしてHIPHOPに出会ったんでしょう?
つやちゃん:
自分のHIPHOPの原体験は、サウスなんですよ。元々はロックを中心にその流れでHIPHOPも聴く、くらいの感覚だったんですけど、2000年代前半にサウスがうわっと来て、そこで「これは大変な音楽が出てきたぞ」って。当時HIPHOPを外から見ていた身として、サウスが主流になって流れが変わった感じがありましたね。
遼 the CP:
サウスの流れで間口が広がったのは色んな方から聞く声ですが、それまでロックを中心に聴いていたつやちゃんさんにとって何が刺激的だったんですかね。
つやちゃん:
自分はサウスの…当時のLil Jonとかを、初めはロックとして聴いていました。エレキギターも入ればガナリ声も入るし、自分がそれまで好んで聴いていたハードコアやメタルっぽい気もして、その辺りのジャンルと地続きで聴いてました。あと、ストーナーロックが好きなんですよね。ドープなギターリフの反復や中毒性を狙った作りが気持ちよくて、そのあたりも自分の中でサウスヒップホップを受け入れる素地を作ったのかもしれないです。そこからはもうDavid BannerにThree 6 Mafiaに……でもなぜかT.Iはあんまりハマんなかったんですよね。自分には泥臭さが足りなかったのかもしれない。後から好きにはなりましたけど、ちょっと時間がかかった。その後、自身の体の芯まで「ラップ」が浸透したなって思ったのはLil Wayneです。もうぶっちきりですね。『The Carter III』(2008年)、これはとんでもない音楽だなと。その後、彼はほんとにHIPHOPとロックを繋げたような『Rebirth』(2010年)もリリースしたじゃないですか…当時は酷評でしたけど。でも、あれも凄くハマった作品でした。元々ジャンルレスに聴いていくのが好きなので、あの時代のサウスは本当に自由な感じが良くて。
で、その頃に日本で初めて本格的にハマったのがSEEDAでした。自分がUSから日本のHIPHOPにシフトするにあたって、そのブリッジの役割を果たしてくれた存在というか。自分は『花と雨』(2006年)とかよりもむしろ『SEEDA』(2009年)の方が好きなんです。その後の作品も大好き。邪道ですよね(笑) その頃にはもう、サウスがどうとかじゃなく色んなスタイルを聴きあさって。一番好きな音楽でありカルチャーはHIPHOPだって、ハッキリ言えるようになった時期でした。
遼 the CP:
これはただの印象論ですが、ダーティサウスの流れや、Trapの隆盛以降も然りですが、それぞれのタイミングでドッとロックから人が流れてくるトレンドがある気がしますね。自分はHIPHOPをHIPHOPとして聴き始めてそのままこの道一本みたいな人間なので(笑)、サウスのHIPHOPの何が(特にロック好きな)人を惹き付けるんでしょう。
つやちゃん:
やっぱり自由さなのかな。ロックが色んな音楽を飲み込んで拡大したり解体したりを繰り返しているように、サウスはそれをもっと直感と反射神経でやってる感じがしませんか?当時、サウスのHIPHOPって、ミュージシャンというよりはむしろアスリートがたまたま音楽をやっているかのような猥雑さを感じたんです。SEEDAのラップも同じで、技巧的なんだけど、単にスキルに回収されないフィジカリティがあって。その後、2015年くらいからMCバトルも盛り上がってシーンがどんどん勢いづいていく中で、USと日本の時差もほとんど感じなくなってきて、日本のHIPHOPをメインに聴くようになった感じです。日本でしか生まれ得ない、というオリジナリティもどんどん出てきて。ここで言うHIPHOPっていうのはラップミュージックであって、今で言うハイパーポップとかも含んでの広い話になってきますけど。
女性のラッパーが抱える二重構造について
遼 the CP:
そうして日本のラップを聴いていく中で、今回のような、シーンにおける女性の問題意識を持ったきっかけはなんだったんでしょう。
つやちゃん:
自分が色んなラッパーの作品を聴いていくうちに、「なんか自分の入れ込み度合いと世間の評価が合わないぞ?」って感じることがたくさん起きてきた。それも女性の作品に多いぞと。もちろんAwichのようにそこが一致するラッパーもいるんですが、一致しないラッパーも多く出てくる中で、これっていわゆるシーンと自分との価値判断の基準がかみ合ってないんじゃないかと思うようになってきたんです。
遼 the CP:
それは生々しいですよね。最初から「このジャンルには問題がある」と喝破して外から切り込んでくるのではなく、好きでそのコミュニティの中に身を浸けていた中で、ふとこの場所の歪さに気が付くというか。
つやちゃん:
HIPHOPに限らずポップミュージックにおけるカルチャ―ってやっぱり凄く大事で、そういった背景にあるものを念頭に置きつつ作品は聴かれていきますよね。男性はそうなってるんですが、女性のラッパーの場合、あまりそういう聴かれ方をされてこなかったのかもしれません。もしくは、女性のリスナーはそこをちゃんと聴いて楽しんできたんだけど、メディアによって書かれたり論じられたりはしてこなかった。例として正しいか分からないですが、リリックにスーパーサイヤ人が並べられた場合と(サンリオのキャラクターである)クロミが並べられた場合、前者はHIPHOPならではの強さとか、他にも「変身」とか「ドラゴン」とか色々な連想が曲を補強していくじゃないですか。一方で、クロミに対してはなかなか難しいわけですよね。でも、実はそこにクロミならではの「いたずらっ子」だったり「病み」だったりの意味性があって、そういうポイントが尖ったビートと絡み合って曲をオリジナルなものにしていたりもする。
遼 the CP:
なるほど。ここで本書のキーメッセージも再度確認させて下さい。「まえがきに代えて」でも書かれていますが、本書はポリティカルな問題意識に踏み込むことを企図したものというよりは、「これまできちんと光の当たっていなかった場所に光を当てる、その結果が女性のHIPHOPアーティストだった」というスタンスですよね?つまり、諸々の問題の入口にすら立つ前に、とにかくまず音楽評論として、あまりに彼女たちが正当な評価を受けていないじゃないかと。
つやちゃん:
そうです。フィメールラッパーって、HIPHOPというマイノリティカルチャーの中のマイノリティという二重構造がありますよね。自身のルーツを見つめながらのし上がっていくということに対して、二重の足かせをはめられながら闘っていかないといけない。そうなると、自分が一体何者なのか、何を愛して何にこだわりを持っているのかというルーツを人一倍掘っていかないといけないし、同時に高いラップスキルも必要になってきます。人種という切り口で考えればそれこそEMINEMだって同じ境遇でしたよね。RUMIもCOMA-CHIも「自分は何者なのか」ということをひたすら掘って掘って、さらにMCバトルという場でラップスキルを客観的に認められることでなんとかのし上がっていった。そこでようやく「男性と同じ」スタートラインに立てた。
遼 the CP:
今回の書籍が「フィメールラッパー批評原論」と銘打ってるのは「本来的な批評そのもの以前に、光が当たってすらいなかった」ということだと書かれてるじゃないですか。これってマーケットの規模の問題もかなりあるとは思うんです。USのメディア事情、カルチャーアーカーイブの現在地がどのようなものか正確に知りませんが、あっちはマーケットは確かにあって、「ヤバければ売れる」だけのパイが存在してる。その中で、売れたアーティストたちは本義的な女性の権利運動に身を投じることが出来る。でも日本の規模だと、そもそもきちんと光を当ててスクープする存在もいなければ、彼女が(あるいは彼でも)ヤバくても食えないほどパイがまだ小さい。だからこそ2022年にもなって、つやちゃんさんがようやく「光を当てる」という、0歩目のような踏み出しをする必要があったというか。
「日本のHIPHOPシーンは大きくなったのか」問題
つやちゃん:
かつ、これは日本に限らないかもしれないですが、HIPHOP内部のサブジャンル化も進んでいるじゃないですか。そこで各サブジャンル間での横断が少なくなってきたり、リスナーも好きなサブジャンル内でとどまってしまったりすることで蛸壺化がどんどん進行していますよね。
遼 the CP:
こうした広い意味での硬直化…隣の畑で何が起こっているのか知ることが出来ない、みたいなことに対して、どんな打ち手があるんでしょうね。部分的な責任は確実にメディアにあるはずだとは思うんです。硬直化じゃなく交流を促す存在として、多面的に良いものを発信していく役割があるべき。もちろんPRKS9もまだまだその責務を果たせるとは言えないと思いますが。もうひとつは…これは責任の話じゃないんですが、サブジャンル間の交流として、今だからこそプロデューサーアルバムって凄く重要な気がします。2021年、KMが『EVERYTHING INSIDE』をリリースしたじゃないですか。
つやちゃん:
大傑作。
遼 the CP:
そう、あれはもう色んな角度から大傑作だと思うんですよ。で、その理由のひとつとして「みんないる」ってことがあると思うんです。つまりC.O.S.A.やCampanella, JJJみたいにオーセンティックなラッパーもいればLEXや(sic)boyみたいな若手もいて、かつNTsKIやMANONみたいにオルタナティブであったり、モデルと活動を並行しているアーティストも参加していて。プロデューサーの力量でもって多様なサブジャンルを一堂に集めてアルバムとして成立させる。それを色んな層のリスナーが聴く。集合地としての重要な意味合いがあるよなあと。
つやちゃん:
確かに、サウンドの凄さに目が行きがちですが、多種多様な場を提供する作品としても機能していますね。ああいうお祭り的なアルバムが最近は少ない気もします。
遼 the CP:
祭り的なプロデューサーアルバムの役割をSpotifyやApple Musicのプレイリストが代替したかとも思ったんですが、プレイリストごとに色が付くことによって、結果的に固まりやすい部分もあるので。
つやちゃん:
もっと大きい視点で見ると、KMはHIPHOPと他ジャンルの壁すらも取っ払ってますもんね。今の蛸壺化問題って、壺の数は多くなってるじゃないですか。だからそれをひとつずつ集めて足していくと「日本のHIPHOPってめちゃくちゃ大きくなった!」と思うんですけど。でも、いかんせんひとつひとつの壺が小さいんですよね。ひとつずつがもっと大きくなっていい。LEXや(sic)boyだって、ほんとはあと10倍売れて良いと思うんです。
遼 the CP:
当たり前に紅白やレコ大にいるべきですよね。「あ、今年もよろしくっす」くらいのノリで普通にいてほしい。それを見てるその辺の人たちとかも「お、今年もLEXか」ってなってるみたいな。
つやちゃん:
そして「フィメールラップ」っていうのはHIPHOP内サブジャンルになってしまっているので、この蛸壺たちをいち視角で切り取ったときのひとつでしかない。今回はこの視角で光を当ててる訳ですけど、本来的にはやっぱりこのひとつひとつの場を大きくしないと、総和は増えないと思うんです。蛸壺化の問題って…私もよくHIPHOP好きの方たちと音楽について話したりしますけど、お互いに好きなもの、知ってるものの対象が違い過ぎて話が噛み合わないとかざらですよね(笑)。
遼 the CP:
その嚙み合わなさをもって「それはシーンが大きくなった証拠だ」って自分も言ったりしますけど、半分正解で半分間違いかもしれないですね。ひとつひとつの蛸壺の中でファンダムが固まっているだけで、それぞれ独立したコミュニティとして存在している。本当は隣に親和性のあるコミュニティがあるのに、そこに気付く手段がない。壺の数を足し合わせるとそれなりの個数・面積になるんでしょうけど、それぞれがあまりに独立したコミュニティとして存在しているというか。
つやちゃん:
好きなものを深掘りしてファンダムを固めるのって、オタク気質な日本人は得意だと思います。一方で内は固めるんだけど、なかなかそれらが外に出てつながっていきづらい。
遼 the CP:
もちろん、アーティストもリスナーも自分に忠実に音楽に向き合ってるだけですからね。外への道筋を作るとか、そういうことって別の大人がすべきことで。
じゃあ誰が、何がシーンを紡ぐのか?
つやちゃん:
大和田俊之さんと磯部涼さん、吉田雅史さんによる書籍『ラップは何を映しているのか』(2017年)では、「日本語ラップにはパフ・ダディがいなかった」って言説が書かれていますね。パフ・ダディがビギ―を連れてきたことで、初めてオーセンティシティと売れるものが結びつくことになったと。アメリカはああいう役割を担うプロデューサー的な存在がいたけど、日本にはそれがいなかった。
遼 the CP:
マス向けにこのカルチャーを伝導する役割を担いつつ、コア層からは後ろ指を指される覚悟も背負って立つ存在というか。こういう話題になると2000年代初頭の盛り上がり…例えばRIP SLYME, KICK THE CAN CREWがどうしたって出てくるわけです。でも、プロデューサーの立場からコンダクトする存在の有無ということで言えばまた違うな。かと言って「バランス感覚抜群な凄腕プロデューサー出てこいや」問題を回避しつつマス層への進撃を考えると、結局「超絶スキルを持った超カリスマラッパーたちが一度に100人くらい出てきて日本の音楽業界を席巻する」みたいな、何も言ってないに等しい案になっちゃう(笑)
つやちゃん:
かつその100人がアベンジャーズ的にくっついたり離れたりしながら話題を提供してくれる、みたいな。でもBAD HOPやAwichの結束ってちょっとそれに近い感じなのかな。あれは感動しますよね。
遼 the CP:
ですね。アーティスト間の交流や音楽外の話題でも耳目を集めつつ、それが音楽面でのマス層への進出と連携している。そうなると…話題の提供による文脈形成で言うと、意外といまシーンに足りないのはゴシップかもしれないですね。もちろん血が流れるような類のものは勘弁だし、アーティストの心身を削る部分と慎重に見極めが必要なんですけど、USのHIPHOPメディアを追ってると「NLE ChoppaがYoungboy Never Broke Againのファンと揉めた」とか「Kanyeの恋仲について新情報」みたいな、割とトライヴァルなニュースが毎日詳報されるじゃないですか。ひとつひとつはスナック菓子でも食べながら横目で消費される記事なんですけど、ああいう音楽以外の周辺環境が文脈を形作る。で、文脈が音楽の聴き方にまで跳ねてくるのがHIPHOP文化でもあることを思うと、カルチャーの積み重ねって、実はゴシップの積み重ねでもあるのかなとか。そう思うとゴシップニュースの量って意外と大事なのかもって最近思ったりします。
つやちゃん:
よく言われることですけど、口語芸能としての位置付けが近いところで、日本ではそのパパラッチされる役目をお笑い芸人が担ってる部分もあると思います。お笑い芸人がスポットを浴びてゴシップメディアにすっぱ抜かれる役割を担ってる。
遼 the CP:
お笑い文化との明確な違いは、HIPHOPは明確にアメリカ発祥のものを日本に輸入してきた点ですよね。俺たちは本場に失礼のないようにする必要がある。である以上、このHIPHOP文化の形を、お笑いのように真に日本のマス層に最適化したものにはいじくれない、というボトルネックがある。
つやちゃん:
もちろん最近ではYouTuberの人たちのラップなんかも出てきてる中で、あの辺りに文化的な連続性があるかと言えばないとは思うんです。それが良いことなのかどうかはさておき、文脈や正統性から離れてラップ、HIPHOPをする流れも出てきてはいる。一方で真面目に向き合ってる人ほど、USのHIPHOPコミュニティのオーソライズを受けたものしか出来ないというジレンマがある。その意識も絶対に大事だとは思うんですが、もう少し楽になって良いんじゃないか、と思うときはあります。
遼 the CP:
それで言うと、ハイパーポップは割と新しい角度からの革命だったかもしれませんね。厳密な意味でのHIPHOPなのかどうかは一旦横に置きますが、スウェーデン発で、SoundCloudで無国籍に伝播して…。
つやちゃん:
だからこそなのか、女性のミュージシャンも多いジャンルでもありますしね。このジャンルやSoundCloudは、比較的制限がない気はします。かと言ってこっちに寄り過ぎると、日本では「本来的な」HIPHOPを求めるカウンターが起きるでしょうし、その辺りはシーソーゲームでしょうね。でも、ハイパーポップはもともとクィア性、包括性といったスタンスを持ちつつその名の通り「ポップ」なので、そのあたりをブレイクスルーする力があるんじゃないかと思います。
遼 the CP:
自国や特定の層に向けたカスタマイズを行うにあたって、ある程度インクルーシブであることでブレイクスルーな力を得るというか。そうなると参考になるのは、ハイパーポップと、それからK-POPかもしれませんね。
先日New York Timesに載っていた記事に、K-POPの作詞作曲をスウェーデンの作家が手掛けるパターンが増えてる、って指摘があったんです。スウェーデンは英語が堪能なこともあって、これまではUSのポップスやR&Bを手掛ける音楽人材も多かった訳ですけど、それがK-POPに流れてきてると。で、なんでかって言うと、「面白い音楽をやってるから」らしいんですよ。俺らってK-POPをよく「洋楽のトレンドに合わせてるから売れる」と語りがちですけど、少なくともスウェーデンの作詞作曲家の卵たちにとっては違うみたいで。HIPHOPもEDMも歌もラップもダンスも混成された、何か聴いたことのないものが爆誕してるように聴こえると。それを面白がって、韓国のマーケットに流れてくる層がリスナー以外にもいる。こういうことを思うと…雑なまとめですけど、自分たちの形に咀嚼したものを出せば、それを面白がる人は国内外に絶対にいるんじゃないかって気もする。
つやちゃん:
新世代のシーンは、既にそういう国内外の差がなく地続きですよね。だから…若い人たちは「HIPHOPとは何か」とか、良い意味で考えてないとは思うんです。どちらかと言うと、自分も含めて(笑)、上の世代がやっぱり一家言あるとは思います。
遼 the CP:
奔放なHIPHOPをしてもオトナが最後にハンコ押してくれないみたいな(笑) これからのHIPHOPが若い世代によってどう改革されていき、それを各世代がどう受容するのかは未知数ですが、確実にうねりは起きてる。日本は人口減少が叫ばれて久しいですが、ことHIPHOPに限って言えば、肌感覚ですが若い世代ほど裾野が拡がりつつある正三角形だと思うんです。日本の人口構造の真逆。HIPHOPはこの構造も武器に、きっとこれからも進み続けるんでしょう。
…とは言え、今回の『わたしはラップをやることに決めた』に立ち戻ると、今のシーンを形作るに至った、偉大な女性アーティストたちの作品があったわけです。後編ではそれを振り返らせて下さい。
つやちゃん:
もう、話したい作品だらけで。クラシックから隠れた良盤、最近のSoundCloud系までたっぷり話しましょう!
▶後編はこちら
───
2022/02/28
PRKS9へのインタビュー・コラム執筆依頼・寄稿などについてはHP問い合わせ欄、あるいは info@prks9.com からお申し込み下さい。
書誌情報:
『わたしはラップをやることに決めた フィメールラッパー批評原論』
つやちゃん[著]
四六判・並製・280ページ
本体2,200円+税
ISBN: 978-4-86647-162-4
1月28日(金)発売
発行元:DU BOOKS 発売元:株式会社ディスクユニオン
https://diskunion.net/dubooks/ct/detail/DUBK320
内容:
マッチョなヒップホップをアップデートする革新的評論集!
日本のラップミュージック・シーンにおいて、これまで顧みられる機会が少なかった女性ラッパーの功績を明らかにするとともに、ヒップホップ界のジェンダーバランスおよび「フィメールラッパー」という呼称の是非についても問いかける。
■RUMI、MARIA(SIMI LAB)、Awich、ちゃんみな、NENE(ゆるふわギャング)、Zoomgalsなど、パイオニアから現在シーンの第一線で活躍するラッパーまでを取り上げた論考に加え、〈“空気”としてのフィメールラッパー〉ほかコラムも収録。■COMA-CHI/valkneeにロングインタビューを敢行。当事者たちの証言から、ヒップホップの男性中心主義的な価値観について考える。■2021年リリースの最新作品まで含むディスクガイド(約200タイトル)を併録。安室奈美恵、宇多田ヒカル、加藤ミリヤ等々の狭義の“ラッパー”に限らない幅広いセレクションを通してフィメールラップの歴史がみえてくる。
目次:
日本語ラップ史に埋もれた韻の紡ぎ手たちを蘇らせるためのマニフェスト――まえがきに代えて
第1章 RUMIはあえて声をあげる
第2章 路上から轟くCOMA-CHIのエール
第3章 「赤リップ」としてのMARIA考
第4章 ことばづかいに宿る体温
第5章 日本語ラップはDAOKOに恋をした
Column “空気”としてのフィメールラッパー
第6章 「まさか女が来るとは」――Awich降臨
第7章 モードを体現する“名編集者”NENE
第8章 真正“エモ”ラッパー、ちゃんみな
第9章 ラグジュアリー、アニメ、Elle Teresa
第10章 AYA a.k.a. PANDAの言語遊戯
Column ラップコミュニティ外からの実験史――女性アーティストによる大胆かつ繊細な日本語の取り扱いについて
第11章 人が集まると、何かが起こる――フィメールラップ・グループ年代記
第12章 ヒップホップとギャル文化の結晶=Zoomgalsがアップデートする「病み」
終章 さよなら「フィメールラッパー」
Interviews
valknee ヒップホップは進歩していくもの。
COMA-CHI 「B-GIRLイズム」の“美学”はすべての女性のために
Column 新世代ラップミュージックから香る死の気配――地雷系・病み系、そしてエーテルへ
DISC REVIEWS Female Rhymers Work Exhibition 1978-2021
あとがき――わたしはフィメールラッパーについて書くことに決めた
解題 もっと自由でいい 文・新見直(「KAI-YOU Premium」編集長)
著者略歴:
つやちゃん
文筆家。ヒップホップやラップミュージックを中心とした音楽、カルチャー領域にて執筆。
「ele-king」「ユリイカ」「文藝」などの雑誌ほかメディアに寄稿。ラッパーをはじめ、宇多田ヒカルなど幅広いアーティストへのインタビューも行う。
- [各アーティスト/レーベル向け]PRKS9に記事掲載する or PRKS9からMVを公開するには:
- Pitch Odd Mansion, HYD?: 2 HORNS CITY #3 参加メンバー全員インタビュー (1)
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。







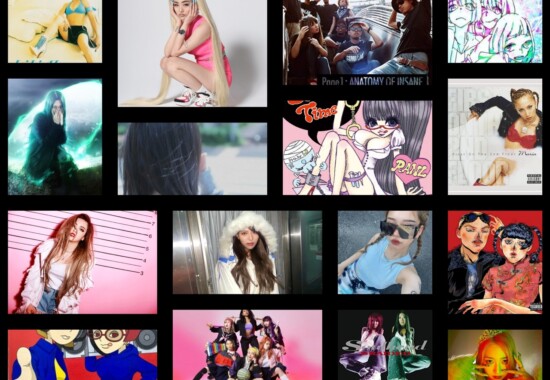


この記事へのコメントはありません。